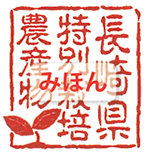
化学的に合成された肥料と農薬両方の使用量を県の慣行基準の1/2以下に抑えて生産した農産物です。
認証機関の審査を受けますので、認証申請料が必要となります。
当協会では、指定認証機関として認証業務を行っております。
申請から認証書を交付するまでの流れは以下のとおりです。
- 申請書類および生産行程管理規程の作成(新規申請)
申請書類及び生産行程管理規程を作成します。申請書類は作成例を参考に、作成してください。生産行程管理規程は、様式を示します。
※申請書類は、申請者の方に作成していただきますが、作成等ができない場合等は当社でコンサルタントサービスを別途行いますのでご相談ください(別途料金必要です)。 - 申請書類の提出
申請書類及び生産行程管理規程を当協会食品環境検査センターに提出します。
受理後、申請者宛に申請料金及び書類審査料金を請求します。 - 書類審査
申請料金及び書類審査料金納金確認後、書類審査を開始します。
管理体制、栽培計画書、ほ場概要書、看板様式等を審査し、基準に適合するか審査します。
書類審査合否の判定を行い、申請者に通知します。 - ほ場・現地検査
書類審査合格の場合、ほ場・現地検査料金を請求し、納金確認後、ほ場・現地検査を開始します。
ほ場・現地検査は、対象となるほ場や関連施設、精米においては精米施設まで検査員が赴き、全てのほ場や施設等の検査を行います。 - 判定
書類審査及びほ場・現地検査の結果を、長崎県農業経営課へ報告し、その後判定員による判定を行います。
- 長崎県特別栽培農産物生産行程管理者認証登録通知書の通知
基準に適合していると判定された場合、長崎県特別栽培農産物生産行程管理者認証登録通知書が通知されます。
不適合の場合、その旨を通知します。 - 通知後
認定生産行程管理者は年1回、栽培実績書及び出荷・販売実績書を作成し、当協会食品環境検査センターへ報告します。
- 有効期間
有効期間は、登録年月日より3年間です。
- 有効期間内の申請書類の内容変更
有効期間内に申請書類の内容変更(生産者やほ場の追加)をしたい場合、「4.ほ場・現地検査」は行わず、書類審査による判定となります。申請時、申請料金及び書類審査料金が必要です。
- 継続申請
3年経過後、継続申請の場合、新規申請の場合とほぼ流れは同じですが、ほ場等の検査はサンプリング検査となります。
申請書類は、期限が切れる1ヶ月以上前に提出してください。
- 申請書類<実績報告書>(Excel/224KB)
- 生産行程管理規程例(Word/51KB)
- 申請書類作成例(Excel/189KB)(実績報告書及び精米の例はありません)
